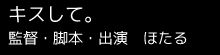「葉月蛍」が女優として僕たちの映画に登場したのはちょうど20年前。
その時と同じ印象を、この「ほたる」監督作でも感じた。
下手くそだなあ。でも妙に味がある。何だか分からない迫力がある。
── 瀬々敬久(映画監督)
男と女が、(長年共に暮らして来て)或る日別れる。
この現代人が数え切れない程繰り返して来た陳腐な場面を、ほたるは堂々と、正面から描く。置く。
それを支えているのは、彼女生来の胆力と、積み重ねて来た、演じる者としての貫禄である。
──沖島勲(映画監督・脚本家)
何年もかかって、ようやく完成した、ほたる脚本・監督・主演作『キスして。』は極私的フィクションとも言うべき美しい映画だ。
ほたるが、葉月蛍だったころや、石井佐代子であることなど、自身をとことん突き詰めていくことで、普遍性ある「おんな」の映画になっていた。
ほたるは、劇中でも元夫に言わせているように、今、大人のおんなになったのだろう。
おんなが愛に目覚めると言うのは、こう言うことなのかと、教えてくれた。
ほたるは、偉い!
──小林政広(映画監督)
いま、結局、つまらないのは男性である。でも、女性だけでは世界は成り立たない。男性のいる場所をどう残すのか。『キスして。』のヒロインは葛藤の奥でそれを考えている。ときには少女のように、ときには女神のように。
──福間健二(詩人・映画監督)
“葉月蛍”のことを“ほたる”と呼ぶのには抵抗があった。
改名について抜き差しならない事情があったとしてもだ。
しかし、この映画を見て初めて葉月蛍がほたるとして生き直さなければならなかった理由がわかった。
彼女はこの映画で自分のどうしようもなさをさらけだし、自分の馬鹿さ加減を真っ直ぐに見つめている。
今いる場所から、強引に自分を引き剥がしても、次の場所が幸せとは限らない。
そこで立ちすくむ彼女の姿に泣いた。
──井土紀州(映画監督・脚本家)
私はこの人の顔を見るとホッとする。いつもこの人の精一杯の心が溢れていて、そこに覚悟を感じるからだ。それは瀬々敬久がこの人を、「大型新人だよ、ガハハッ」と言って笑った20年前のあの時から、今も変わることなくずっとそうだ。「私は大丈夫だから遠慮なく」と言っているようで、時に私は仕事の上だが言い過ぎてしまい、この人を困らせたりした。すみませんでした。この覚悟の人が誰にも甘えないで一人映画を作った。自身に起きたことをその覚悟で受け止め、長い歳月をかけてそれらを新しい物語へと昇華させることに成功した。映画『キスして。』は、だからこそ愛おしい。
──サトウトシキ(映画監督)
伊藤猛が、ほたるさんが、ただただ素晴らしい。自由なのだと思う。
ぎこちなく立ち現れる抒情は主観的な感情過多と正反対の体験なのだと思う。
海はワンカットも映っていないのだが磯の潮の匂いが立ち込めて来る。
──鎮西尚一(映画監督)
「歳を重ねてから好きな人ができるっていろいろ大変ですよね。
そのことを映画にするのは、さらに大変なことだなあと。
ほたるさんはそれを、いじいじと、でもあっけらかんと見せてしまうのですなあ」
──七里圭(映画監督)
ほたるのやわらかな微笑みや伊藤猛のレンズを貫く目に訳もなく、泣く。身近にいながらそれさえ撮り得なかった自分に深い疑いを抱き、「映画」について何も知らない自らの愚かさに繰り返し気づかされ、痛飲。「1,2,3,4,5」、体の底から動揺、崩れ落ちる。
──堀 禎一(映画監督)
ほたるさんの空間や息づかいはひややかに冷めた体温に灯をともす。女にすべてをゆだねた男たちの顔はなぜ色っぽいのだろう。 過去と未来の痕跡をかき混ぜて、 情念をフィルムに焼き尽くすようにただそこに在ることで満足できないほたるの逆襲。
──小野さやか(映画監督)
冒頭から惹き付けられました。
凄く普通で、身近で、でもちょっと謎めいて。
どこかいびつな主人公。
幸せと恐ろしさが交差する生々しい日常と、幻想的で詩的なシーン。
流石ほたるさん!
──稲葉まり(アニメーション作家、アートディレクター)
『ほたるさんは、不思議なひとだと思っていた。
暗闇を必要としなくなった映画が多いなかで、
暗闇に息を潜める映画ですね。
K’sシネマの暗闇で、ね、「キスして。」』
──矢崎仁司(映画監督)
真っ正直ないい映画でした。
続きが見たい、もっとみたいと思いました。
あれはどんなふうに撮ったんですか、とか、この後どうなるんですか?とか(この先
のほたるさんの動向も含めて)いろいろ聞きたくなってしまうような、とにかく気に
なる映画です。
──西山洋市(映画監督)
ほたるさんの声が好きです。
その声が語る言葉のひとつひとつが、これまでのどの作品よりも、
真っすぐに届いてきた気がしました。
──那須千里(映画ライター)
他者(男)の欲望のために役柄としての女を演じるのではなく、
自身の女としてのリアルな欲望を晒すために裸になった“ほたる”が、ここにはいる。
未熟ではあるが、その裸の姿は、未熟だからこその瑞々しさと荒々しさに満ちている。